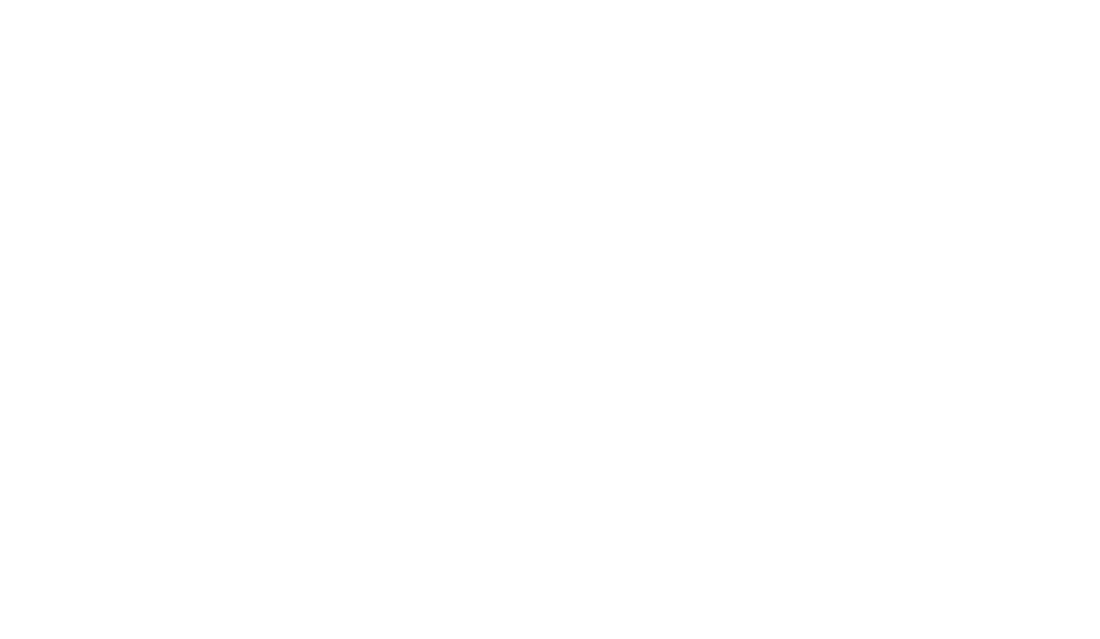七月八日 愛の律法に生きた人 パート2(二〇一二年七月 ひとしずく八六九)
これは、上杉鷹山がその領民に宛てた教えの抜粋です(「代表的日本人」から)
「たがいに怠らず、親切を尽くせ。もしも年老いて子のない者、幼くて親のない者、貧しくて養子の取れない者、配偶者を亡くした者、身体が不自由で自活のできない者、病気で暮らしの成り立たない者、死んだのに埋葬できない者、火事にあい雨露をしのぐことができなくなった者、あるいは他の災難で家族が困っている 者、このような頼りのない者は、五人組が引き受けて身内として世話をしなければならない。五人組の力が足りないばあいには、十人組が力を貸し与えなくてはならない。もしも、それでも足りないばあいには、村で困難を取り除き、暮らしの成り立つようにすべきである。もしも一村が災害で成り立たない危機におちいったなら ば、隣村は、なんの援助も差し伸べず傍観していてよいはずがない。五カ村組合の四カ村は、喜んで救済に応じなくてはならない。」
以下は、上杉鷹山の人柄をよく物語るエピソードです:(インターネットから)ある老婆の手紙
「安永六年十二月六日(一七七八年一月四日)、米沢西郊の遠山村(米沢市遠山町)のヒデヨという老婆が、嫁ぎ先の娘に宛てて書いた手紙が残っている。
『ある日、干した稲束の取り入れ作業中に夕立が降りそうで、手が足りず困っていたが、通りかかった武士二人が手伝ってくれた。取り入れの手伝いには、お礼として刈り上げ餅 (新米でついた餅)を配るのが慣例であった。そこで、餅を持ってお礼に伺いたいと武士達に言ったところ、殿様お屋敷(米沢城[9])の北門に(門番に話を通しておくから)というのである。お礼の福田餅(丸鏡餅とき な粉餅の両説あり)三十三個持って伺ってみると、通された先にいたのは藩主治憲 (上杉鷹山のこと)であった。お侍どころかお殿様であったので腰が抜けるばかりにたまげ果てた上に、(その勤勉さを褒められ)褒美に銀五枚まで授けられた。その御恩を忘れず記念とするために、家族や孫たちに特製の足袋を贈ることにしたのである。』講談「水戸黄門漫遊記」のように、お忍びの殿様が庶民を手助けしてくれる話はよく語られるが、こうした実例が示されることは他に存在しないであろう。」
「受次ぎて 国の司の身となれば 忘るまじきは 民の父母」
鷹山が十七歳で第九代米沢藩主となったときの決意を込めた歌である。藩主としての自分の仕事は、父母が子を養うごとく、人民のために尽くすことであるという鷹山の自覚は、徹底したものであった。
藩主とは、国家(=藩)と人民を私有するものではなく、「民の父母」としてつくす使命がある、と鷹山は考えていた。しかし、それは決して民を甘やかすことではない。鷹山は「民の父母」としての根本方針を次の「三助」とした。すなわち、
・自ら助ける、すなわち「自助」
・近隣社会が互いに助け合う「互助」
・藩政府が手を貸す「扶助」
「自助」の実現のために、鷹山は米作以外の殖産興業を積極的に進めた。寒冷地に適した漆(うるし)や楮(こうぞ)、桑、紅花などの栽培を奨励した。漆の実からは塗料をとり、漆器を作る。楮からは紙を梳き出す。紅花の紅は染料として高く売れる。桑で蚕を飼い、生糸を紡いで絹織物に仕上げる。鷹山は藩士達にも、自宅の庭でこれらの作物を植え育てることを命じた。武士に百姓の真似をさせるのかと、強い反発もあったが、鷹山自ら率先して、城中で植樹を行ってみせた。この平和の世には、武士も農民の年貢に徒食しているのではなく、「自助」の精神で生産に加わるべきだ、と身をもって示したのである。やがて、鷹山の改革に共鳴して、下級武士たちの中からは、自ら荒れ地を開墾して、新田開発に取り組む人々も出てきた。家臣の妻子も、養蚕や機織りにたずさわり、働くことの喜びを覚えた。」
「米沢城外の松川にかかっていた福田橋は、傷みがひどく、大修理が必要であったのに、財政逼迫した藩では修理費が出せずに、そのままになっていた。この福田橋を、ある日、突然二、三十人の侍たちが、肌脱ぎになって修理を始めた。もうすぐ鷹山が参勤交代で、江戸から帰ってくる頃であった。橋がこのままでは、農民や町人がひどく不便をし、その事で藩主は心を痛めるであろ う。それなら、自分たちの無料奉仕で橋を直そう、と下級武士たちが立ち上がったのであった。「侍のくせに、人夫のまねまでして」とせせら笑う声を無視して、武士たちは作業にうちこんだ。やがて江戸から帰ってきた鷹山は、修理された橋と、そこに集まっていた武士たちを見て、馬から降りた。 そして「おまえたちの汗とあぶらがしみこんでいる橋を、とうてい馬に乗っては渡れぬ。」と言って、橋を歩いて渡った。武士たちの感激は言うまでもない。鷹山は、武士たちが自助の精神から、さらに一歩進んで、「農民や町人のために」という互助の精神を実践しはじめたのを何よりも喜んだのである。」