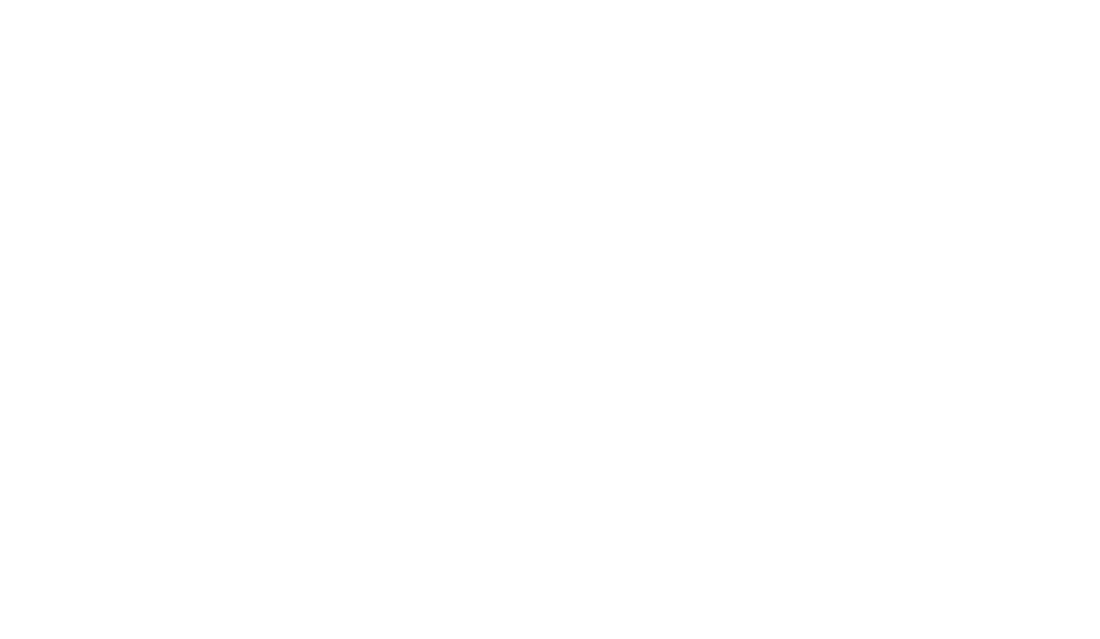七月三日 本当の教育 (二〇一二年七月 ひとしずく八六三)
「少年よ、大志を抱け!」で知られるクラーク博士。彼は、素晴らしい教育観をもって日本にやってきました。その感動のエピソードを紹介します。(11年の間、台湾の総統であった李登輝氏の著した「『武士道』解題」(小学館)から引用したものです。)
「新設大学の学長としてクラークは大いに腕をふるい、理事会や学生たちから高い人望を得た。吉田公使は、人物、識見ともにすぐれたクラークをぜひ札幌農学校に迎えたいと考えて交渉を始めたのである。しかし、交渉は難航した。クラークは現職の学長であり、しかも学内で評価が高かったために理事会は許可を出そうとしなかった。これを押し切ったのは、当のクラークであった。フロンティア・スピリットに溢れたクラークは、東洋の新興国が進めようとしている一大事業に強く心を動かされた。これぞわが仕事だと思ったのだ。クラークはこの申し出に異常なほどの熱意を表明し、彼自らも理事会の説明に当たった。その結果、ついに理事会は折れて、現職の学長のまま一年間日本に赴く、という異例の契約が調印されたのである。
クラークは道徳教育と人格の陶冶(とうや=育成のこと)に力を注ごうとしていた。その一端は、開校直後の訓辞に表れている。当時、日本の学校は細かな規則を設けて生徒の一挙手一投足を縛ろうとする弊があった。他律の教育観である。「札幌農学校」の前身の「札幌学校」もその方針であった。しかし、クラークはこうした教育観とまっこうから対立する。彼の信念は自立の教育観であった。彼は生徒たちの良心ある行動を信じた。他から命じられて何かをする。あるいは他から強制されて正しい行動をするようでは独立した人格たりえないとした。自らの良心に従い、自発的に責任ある行動をとるようでなくては「近代人」とはいえない。「札幌農学校の生徒たちにはそのような人間になったほしい」という期待が、クラークにはあった。したがって、彼は生徒たちが覚えきれないようなたくさんの校則をいっさい廃棄し、ただ一言、「ビー・ア・ジェントルマンBe a gentleman(紳士たれ)」と、述べただけだった。当時としては画期的な校則だった。
このクラークの発言は、生徒たちを感動させた。彼らも全幅の信頼を寄せるクラークに応えていこうと決心したのだ。
「私たちは、ジェントルマンとして俯仰天地に恥じない行いをしなければならない」と固く心に決め、自らの行動を律していった・・・大学学長という栄光の座を抛(ほう)って酷寒の札幌に住み着いたウィリアム・クラークの熱意と誠実さには並はずれたものがありました。敬虔なクリスチャンでもあった彼は、早くから、「物質的な発展や近代化もさることながら、あくまでも国造りの根幹となるのは人間なのだから、精神的な成長や発展こそが他の何よりも大切だ」という固い信念を持っており、横浜の街に降り立つや否や、直ちに数十冊の英文の「聖書」を買い入れ、それを抱えて北海道に急行しました。そして、札幌農学校の開校式が終わるとすぐに、第一期学生十六名全員に一冊ずつ手渡して、毎回、正規の授業を始める前に必ず、「聖書」の輪読会を行ったのです。それまではキリスト教とは縁もゆかりもなかった旧武士階級の子弟たちでしたが、いつの間にか自分の姓名までしっかりと書き込んでくれていた真新しい「聖書」を開いて、今さらながらのようにクラーク博士の温かくも気高い精神に深く感動して、熱心に読み耽るようになっていきました。
しかし、このことを知った黒田清隆長官は大いに驚き、かつ慌てたのです。三百年の鎖国時代を通じてずっと「ご禁制」とされてきたキリスト教が解禁となったのは、明治六年(一八七三 年)になってからのことです。ましてや、硬骨の黒田は名うての「キリスト教嫌い」で通っていたのです。「こともあろうに、官立の学校で聖書を読ませるとは何事か」とばかり、クラーク博士を官邸に呼びつけ、「直ちに輪読会を中止せよ」と厳命を下しました。しかし、クラークは一歩も後へ引こうとはせず、逆にこう言い切ったのです。
「これは異なることを承るものです。あなたは、かつて私にこう言ったではないですか。『クラーク先生をはるばる日本にお招きするのは、ただ単に日本の未来を背負って立つべき有為の青年たちに知識を授けていただくだけではなく、徳育を施してもらいたいと思ったからこそです』。私がクリスチャンであることは、あなたも先刻ご承知のはずです。クリスチャンにとって、徳育を授ける道はただ一つしかありません。『聖書』 の教えを徹底的に説くことです。それがお気に召さないなら、私にはとてもこのたびの大任を果たす自信などありません。直ちに解任してくださって結構です」
さすがの黒田清隆も、これを聞いてすっかり参ってしまいました。しかも、もともと典型的な薩摩隼人のことですから、いったん了解すると後は竹を割ったようにさっぱりした性格で、「わかりました。そのようなことなら黙認することと致しましょう・・・」
と承諾したのでした。
・・・アメリカに帰国する日が差し迫った明治十年の三月に、クラーク博士は、自らの手で「イエスを信ずる者の契約」をしたため、「これに同意できる人だけサインしてください」と呼びかけました。すると、どうでしょう、第一期入学の十六名全員が先を争うようにして署名したのです。有名な「ボーイズ・ビー・アンビシャス」という言葉を残して、クラーク博士が帰途についたのは、それから一ヶ月も経たぬ四月のことでしたが、その直後に初めて北海道の地にやってきたのが、新渡戸稲造たち第二期生たちだったのです。
実に意外なことではありますが、かの有名なウィリアム・クラーク博士と、新渡戸や内村ら後の日本におけるキリスト教布教の中核となるべき若者たちは、たった一歩の違いで顔を合わせる機会はなかったのです・・・
しかし、ここが、「精神教育」の素晴らしいところで、クラーク博士の謦咳(けいがい)に接することなど全くなかったにもかかわらず、その高貴な魂と生き方は、第一期生十六名の先輩たちを通じて見事にバトンタッチされ、やがて『武士道』や『代表的日本人』などという素晴らしいメッセージが、日本から世界に向けて発信される原動力となったのです。」
若者の魂に神の言葉を伝えるという使命を持った一人の人のおかげで、一握りの学生が希望を持ち、神に従う決意をしました。そして、それはさらに他の人へと伝わって行き、そこから日本を真理に基づいて新しく造りかえる、幾人もの偉人たちが生まれたのです。
私はこれこそが、本当の教育ではないかと思いました。
精神教育というものがいかに大切なものであるか、またそれは、何を礎にしての教育であるべきなのか、真剣に考えさせられます。
今わたしは、主とその恵みの言とに、あなたがたをゆだねる。御言には、あなたがたの徳をたて、聖別されたすべての人々と共に、御国をつがせる力がある。 (使徒行伝二〇章三二節)
だから、すべての汚れや、はなはだしい悪を捨て去って、心に植えつけられている御言を、すなおに受け入れなさい。御言には、あなたがたのたましいを救う力がある。 (ヤコブ一章二一節)