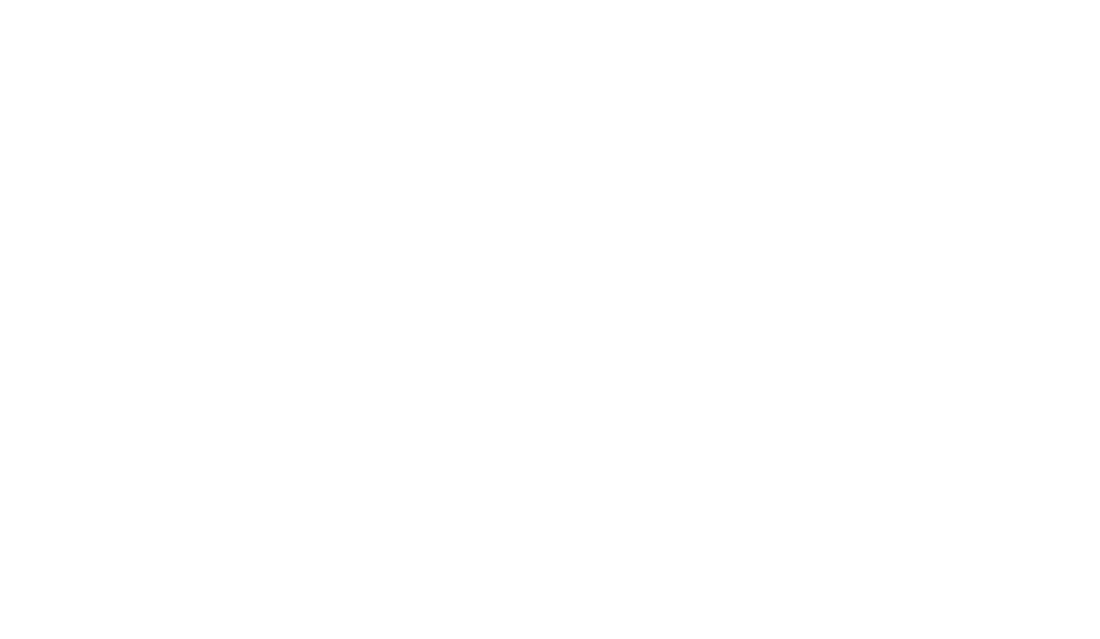三月二四日 天にのぼっても陰府にくだっても パート2
<二〇一三年三月 ひとしずく一一〇八 (小山晃佑著「眠れない夜」の「天にのぼっても陰府にくだっても」からの引用の続き>
天にいっても陰府に行っても神に出会うということは、よろこびと驚きのメッセージ。天に行ったら天があったというのなら何も騒ぐ必要はない。ところがこの天に行ったら天があったということがまた大切なことなのである。
木に行ったら木があった。水に行ったら水。川に行ったら川。山に行ったら山。
山に行ったら神に出会ったという事では話がこみいってくる。そして川に行ったら神に出会ったでは話がこんがらがってくる。気をつけないと山の神、川の神というものがでてくる。山に行ったら山。川に行ったら川の方がすっきりしていてよいのである。
私はこのすっきりさは人間の精神生活の上に大切なことであると思う。近代的人間というものはこのようにすっきりしたものを持っていなくてはならない。
そうなると一体この昔の詩人は何をここで歌っているのだろう。まず第一に神から逃げかくれはできない、悪いことをしたらつかまえてやるぞというお方でないこと。
第二に天に行っても神の御前にあるし、陰府に行っても神の御前にあるということは、天専門の神、陰府に当直の神というようなことではなくしてすべてのものの創造者なる一つの神の姿を示したもの。
ですから神は天より偉大であります。神は陰府にくっつけられていません。全ての者を超越しているお方であります。すべてを超越しているお方はすべてに対して自由です。そしてその自由を持ってすべてのところで私たちに出会い給うのです。
「わたしが天にのぼってもあなたはそこにおられます」というのは、あなたは天に配置された神であるというのでなく、自由を持ってそこでも私たちに会い給う神であるというのです。いやいやながらではありません。そこにずっといるからでもありません。神は自由なお方です。
自由の意味はなんでもできるということではありません。そういうことなら気儘勝手ということと自由はくっついてきます。自由の深い意味は他者のために自己の自由をよろこんで制限するという自由であります。このとき本当の自由が姿を現します。
この全く簡単な詩人の言葉の中には、このような真の自由の姿を遠くから指さしているものがあります。自己の自由を他者のために制限する自由こそ、聖書の言わんとする自由です。そこにはすでに他者を大切に―重大に―見るという姿勢が現れています。「つかまえてやるぞ」と大変異なります。
すべてのものの創造者なる神の自由とはこのような自由であるのです。創造ということは、聖書では神がそのおつくりになった一切のものと交際の関係に入るということを意味しています。
神はつくりっぱなしのお方ではないのです。つくられたものと関係に入り給うということは、すでに自己の自由を限定されているということであります。
これが愛ということです。創造ということと愛ということはこのように同時に起こるのです。他者のために自己を制限することが愛でしょう。創造とはまさにそのようなことなのです。お母さんが赤ん坊を生んだときからお母さんはいろんな点で自己制限をします。そうでなかったら赤ん坊の世話をすることもできないし、またそうでなかったら赤ん坊は育たないでしょう。こんな私に、都合の悪いときにミルクを欲しがってはだめ、といってたら赤ん坊は育ちません。
お母さんは自己限定をしなくてはなりません。このようなことを愛と言います。自己を他者のためによろこんで制限することを離れて、愛というものはないでしょう。これが愛が単にロマンティックな感傷的なものでないという理由なのです。
私は制限とか限定とかいう表現を使いましたが、愛が強度になったとき他人のために自己を放棄するというようなことが起こってきます。聖書はこういうことがキリストにおいて起こったのだと告げるのです。キリストは自己制限や限定をつきぬけて自己放棄にまでゆき給うたのです。
人が友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。(ヨハネの福音書十五章十三節)
しかし、まだ罪人であったとき、わたしたちのためにキリストが死んで下さったことによって、神はわたしたちに対する愛を示されたのである。(ローマ五章八節)
「友のため」に生命を捨てることが大きな愛なのに、キリストは「罪人のため」に生命を捨てる。こういう愛にぶつかる。
私が天にのぼるとそこには天がある。しかしその天で私自身を深く反省し考えてみると、私という他者のために生命を放棄するまで愛してくれた人のいることを思う。このような人とつながりを持つということが、私自身の私自身を見る見方を根本的に変えてしまった。私という人間はそんなに強い愛の対象なのだろうか。私という人間はそんなに大切な人間なのだろうか。人間がゴミのように取り扱われている世の中で。これまた何という音信だろう。
私が陰府に行くと、なるほどそこには陰府がある。陰府は陰府。しかしそこで私を根本的にくりあげているものがなんであるかを考えてみる。それは陰府でなくて、私という他者を愛してくれた者との関係である。この愛してくれた者は自己を限定したお方、いや、放棄までしてくれたお方である。
どこに行ってもいつでもこのように考えることがよろこびである。忘れてしまっていても、時々なにかのことにかかわってこのことを思い出すと喜びが帰ってくる。一年一度でもよい。よろこびがそこにある。五年に一度。いや十年に一度でもそのよろこびは十年の荒波と混乱の中を旅してゆく力を与えてくれる。
いつもは忘れている。天にのぼるような時―非常時―私たちはそれを思い出す。いつもは忘れている。陰府に下るような時―非常時―私たちは自分という他者を愛して下さった誰かのいたことを思い出す。こんなことを詩篇の詩人は美しい言葉をもって歌ったように思えます。