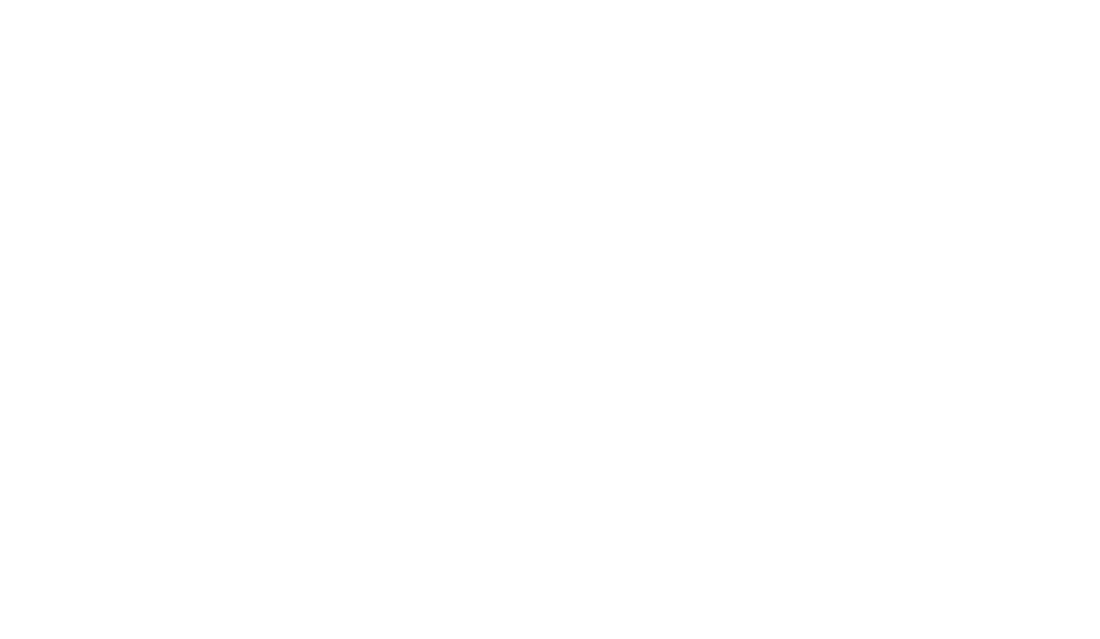Ⅱ. 神の位格:三位一体<8>
神についての研究
ロバート・D・ルギンビル博士著
- 聖書における三位一体<d>
3) 聖霊(三位一体の第三位格):
– 起源: 旧約聖書の第一章(創世記1章2節)から新約聖書の最終章(黙示録22章17節)まで、「霊」という言葉は聖霊なる神を指して使われています。ヘブル語とギリシヤ語で「霊」を意味するruachとpneumaという言葉は、それぞれ「風」または「そよ風」という意味が核となっています。そして、この名称の例えからも、重要な点が汲み取れます。
– 意義: 風は強力で目に見えない力です。 私たちはそれを知覚し、その影響を経験しますが、それがどこから来るのか、またどこへ向かっているのかはわかりません(ヨハネ3章8節)。 風は、穏やかで暖かくするものから、強力で怖ろしいものまであります。 「風」は、神のご計画における聖霊の役割を的確に表現しています: 神のご計画を推進する上で、その目に見えない力強い善への働きかけ(ゼカリヤ4章6節; 第一コリント12章3節)と悪の抑制(創世記6章3節; 第一コリント12章3節; 第二テサロニケ2章5-8節)を過小評価してはいけません。
– 位格: 聖霊はしばしば三位一体の第三人称(すなわち、目に見えない「彼」<著者は英語で「he」を使っています>という方)と呼ばれます。なぜなら、御父と違って、聖霊は私たちに直接語りかけることはなく、御子と違って、聖霊は私たちに現されることはないからです: むしろ、風のように、私たちの目には見えない存在ですが、だからといって、私たちがとても個人的で生き生きした形で、主の力を経験しないわけではありません。(ヨハネ14章16-17節; ガラテヤ5章22-26節)
注意: 上記の説明で明らかなように、父、子、聖霊という名前は、人類に対する神のご計画における三位一体のそれぞれの役割を代表するものであり、そのご計画における三つの神の位格の関係と働きを理解する助けとなるように与えられたものです。 これらの名前自体は、上記で概説したように、明らかに人間の参考基準として意図されたたとえの枠を超えて拡大解釈されてはなりません。これは軽視できる問題ではありません。なぜなら、過去の異端がキリストの完全かつ等しい神性を否定しようとしてきたのは、主に「御子」という称号を根拠としていたからです(例えば、超アリウス主義のように、父なる神に本質的に従属する存在としてキリストを位置づけるなど)。聖霊の例は、これらの称号のみに基づいて行われる分析がいかに見当違いであるかを示しています。なぜなら、聖霊は、私たちのキリスト教的生活における目に見えないけれども強力な役割を適切に表現する言葉として「風」が用いられるとしても、決して「無生物」でも「非人格的」でもないからです。 御霊は、私たちに対して、また三位一体の他の位格に対して、非常に個人的な方法で働き(ヨハネ3章5節, 14章16-17節, 14章26節, 15章26節, 16章8-15節; 使徒行伝5章3節, 5章9節, 13章2節, 16章6-10節; ローマ8章26節; 第一コリント2章10節; 黙示録2章7節)、私たちの慰め主、励まし主(ヨハネ14章16節, 16章7節)として働かれます。 私たちが聖霊から受けるリーダーシップ(ローマ8章4節; ガラテヤ5章16節と18節)、励まし(ヨハネ14章16節, 16章7節; 第二コリント1章3-7節参照)、力づけ(ルカ24章49節; ローマ15章13節)の関係は、私たちが地上で経験することのできる最も 「個人的」で「生き生きとした」関係です。
<三位一体-9>に続く